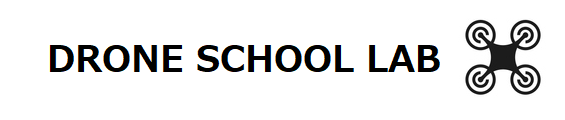コラム
ドローン空撮時にプライバシーを侵害しないためのポイント
投稿日/2025.10.24

ドローンは、上空から遠隔で広範囲を撮影できるという特性を持ちます。その自由度の高さゆえ、他人の敷地や生活空間を意図せず撮影してしまい、「プライバシー侵害」として問題になるケースも少なくありません。
実際に、有名人の自宅が無断で報道されトラブルになるなどといったニュースがあり、社会的な関心も高まっている問題です。
本記事では、ドローン撮影におけるプライバシー侵害の定義や、実際に起きたトラブル、そして安全に撮影を行うためのポイントを解説します。
この記事の目次
ドローン空撮で問題となる「プライバシー侵害」とは

一般的にプライバシー侵害は「私生活をみだりに公開されない権利」(民法709条の不法行為に基づく判例上の権利)に基づき損害賠償請求が可能な権利です。
「ドローンによるプライバシーの侵害」として法律上の明確な条文はありませんが、他人の私生活や居住環境などを、本人の承諾なく撮影・公開してしまうことはプライバシーの侵害だといえるでしょう。
たとえば、自宅の庭やベランダ、洗濯物、個人の顔・姿など、個人が特定できる映像を無断で撮影・公開する行為は、プライバシーの侵害とみなされる可能性があります。
似た概念として「肖像権」もありますが、これは「自分の姿を勝手に撮られない、写真や映像を無断で公表・利用されたりしない権利」であり、プライバシー侵害よりも範囲が広い点が特徴です。
ドローンは上空から広範囲を撮影できるため、意図せず他人の生活空間を写してしまうリスクが高くなります。撮影者は「どこを撮るか」だけでなく「誰が映り込むか」にも十分な注意が必要です。
ドローン空撮で「プライバシー侵害」としてトラブルになった例
2024年、プロ野球選手として活躍する大谷翔平選手の新居をめぐるドローンでの報道が、大きな社会的議論を呼びました。記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。
日本のテレビ局2社が、ドローンによる空撮映像を含む形で大谷選手の新居を紹介し、自宅の場所や外観が分かる状態で放送したことで「報道目的を超えたプライバシー侵害ではないか」と批判が殺到しました。
最終的には、テレビ局が番組内や社長会見で謝罪するに至っています。
また、今年の2025年5月には、ブラジルの民家をグーグルのストリートビュー画像で掲載したgoogleが、約186万円の賠償金と画像削除を命じられています。
ドローンで撮影したものではありませんが、自宅の庭において全裸で過ごしていた男性が、ストリートビュー画像に写り込んでしまっていたというものでした。
(参考:《ブラジル》グーグルに賠償金支払い命令=ストリートビューに全裸男性)
どちらの事例も、技術や報道の自由が拡大する一方で「どこまでが私的な領域なのか」という境界が曖昧になっている現状を示しています。撮影者やメディアには、個人の尊厳を守る配慮がより強く求められているといえるでしょう。
ドローンのプライバシー侵害問題にはガイドラインがある
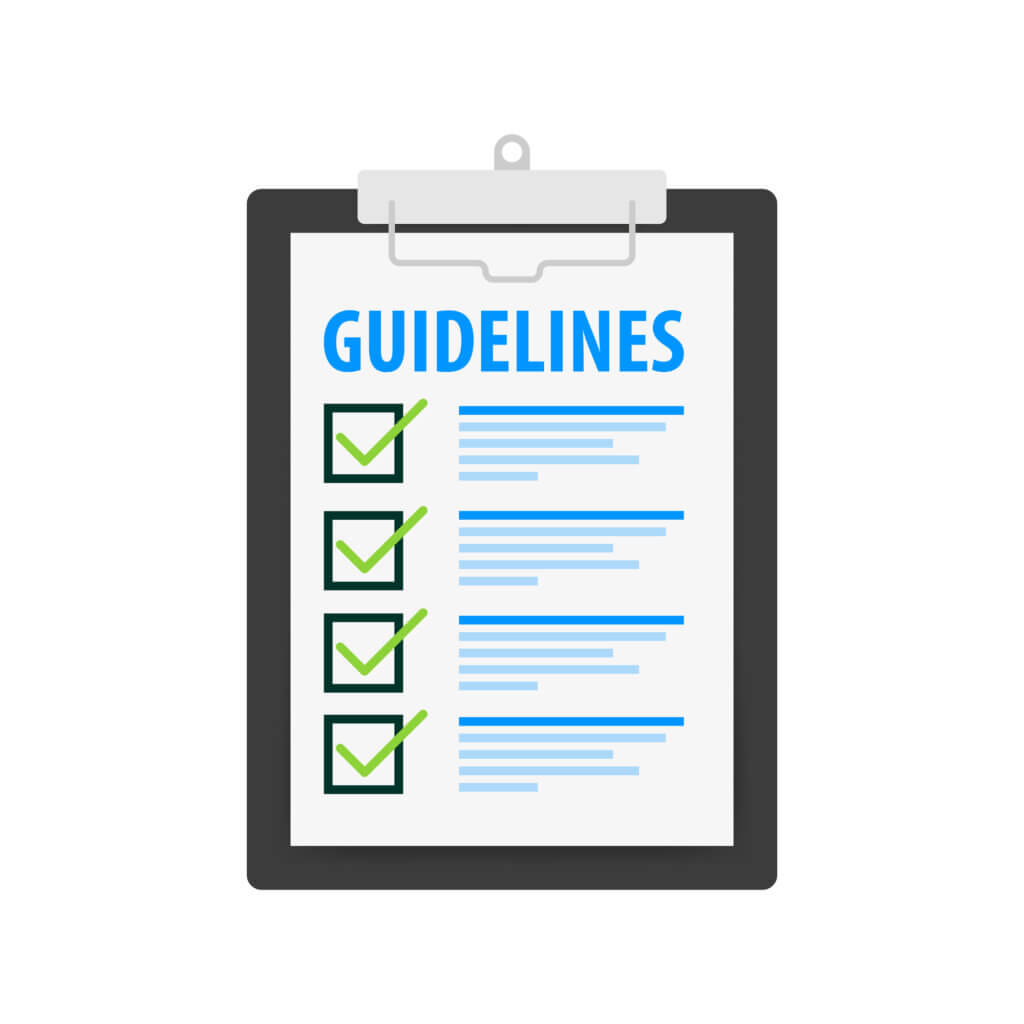
ドローンを使った撮影によるプライバシー侵害を防ぐため、総務省は2015年6月に「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン(案)」を公表しています。
このガイドラインでは「ドローンによる撮影行為は、プライバシーや肖像権を侵害する可能性がある」という前提のもと、撮影者が守るべき基本的な考え方が示されています。
まず、撮影が違法にあたるかどうかには明確な線引きがなく、撮影の目的・方法の妥当性や、対象にどのような情報が含まれているかを総合的に判断するとされています。
そのうえで、「他人に知られたくない情報」である場合は、プライバシーとして保護される可能性が高くなります。たとえば、個人宅の外観を住所とともに公表することや、屋内の様子、車のナンバー、洗濯物などが写っている映像は、内容次第で侵害とみなされることがあるのです。
また、肖像権についても「人はその承諾なしに容貌や姿態を撮影・公開されない権利を持つ」と明記されています。ただし、特定の人物を狙った撮影でなく、街並みなどを一般的に撮影する中で偶然映り込んだ場合は、容貌が判別できないようぼかし処理などを行うことで、社会的に許容される範囲内と考えられます。
つまり、ドローン撮影では「どのように撮るか」と同じくらい「何が写り、どう公開するか」にも慎重な配慮が求められます。
ドローン空撮でプライバシー侵害をしないためのポイント

ドローンによる空撮を安全に行うためには、法令を守るだけでなく、周囲の人々のプライバシーに十分配慮する姿勢が欠かせません。
「悪気がなかった」としても、撮影内容によっては思わぬトラブルに発展することがあります。
ここでは、撮影者が実践できる、以下5つの基本ポイントを紹介します。
■ 撮影場所と対象を明確にして、周囲への配慮を徹底する
■ 飛行ルート・カメラの向き・高度に注意する
■ 撮影後は映像の確認と編集でプライバシーを保護する
■ 公開前に第三者の目で最終確認を行う
■ 公開後に権利侵害がわかったら速やかに削除・対応する
これらのポイントを押さえ、プライバシーをめぐるトラブルを未然に防げるようにしていきましょう。
撮影場所と対象を明確にして周囲への配慮を徹底する
撮影を始める前に、まず「どこを」「何を」撮るのかを明確にしましょう。住宅地や人の生活圏が含まれる場合は、映り込みの可能性を考慮して構図を検討することが大切です。
管理者への事前許可はもちろん、近隣住民への声かけもトラブル防止につながります。特に個人宅や車のナンバー、人物の顔が特定できるような映像は、後の権利侵害の火種になりやすいため注意が必要です。
飛行ルート・カメラの向き・高度に注意する
撮影中のトラブルを防ぐには、飛行ルートやカメラの角度を事前にシミュレーションしておくことが有効です。
比較的高い高度からの撮影は、広範囲の住宅や人を映し込んでしまうリスクがあります。ドローンのジンバル角度を細かく調整し、必要のない範囲を映さないよう心がけましょう。
また、風や天候による機体ブレで意図せず他者の敷地を撮ってしまうケースもあるため、環境条件の確認も欠かせません。
撮影後は映像の確認と編集でプライバシーを保護する
撮影後は、映像内に個人が特定できる要素(顔・車のナンバー・表札・洗濯物など)が含まれていないかを丁寧にチェックします。
問題がある場合は、モザイク処理やトリミングで対応しましょう。商用利用の場合、使用範囲をクライアントと共有し、万一の責任範囲を明確にしておくことも大切です。
編集段階での確認を怠ると、公開後の削除対応に追われるリスクがあります。
公開前に第三者の目で最終確認を行う
自分では気づきにくい映り込みや情報流出を防ぐため、チーム内または第三者によるチェックを行うと安心です。
撮影者の主観だけで「問題ない」と判断せず、他者の視点から見て不快感や違和感がないかを確認しましょう。
特にYouTubeやSNSなど不特定多数に公開する場合は、公開範囲(限定公開・非公開)も含めて慎重な設定が求められます。
公開後に権利侵害がわかったら速やかに削除・対応する
万が一、映像公開後に「プライバシー侵害ではないか」と指摘を受けた場合は、速やかに動画を削除または非公開にし、関係者に連絡を取りましょう。
対応が遅れると、炎上や損害賠償のリスクが高まります。
誤解であっても、誠実な対応姿勢を示すことが信頼につながります。撮影データや許可書類を適切に保管しておくことで、後から説明が求められた際にも冷静に対応できます。
まとめ
ドローン撮影では、操縦者の意図に関わらず、他人の生活空間や個人を特定できる情報を撮影してしまうおそれがあります。
撮影前の下調べ、編集時の映り込み確認、公開後の迅速な対応など、どの段階でも「他人に知られたくない情報を扱っていないか」という視点を持つことが重要です。
プライバシー侵害かどうかの判断は、撮影の目的や方法、映像の内容などを総合的に見て判断されます。ガイドラインを理解し、慎重に対応することで、不要なトラブルを防ぎ安心して撮影ができるようにしていきましょう。